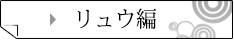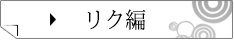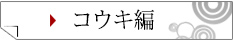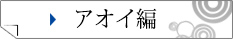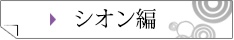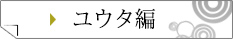『異性との距離間』
これは、まだ私達の秘密が明かされる前の話――
その日、私と彼女は街の景色を見渡せる丘の上に来ていた。
「とっても綺麗ですね! シェアハウスはあの辺りでしょうか?」
「いや、正しくはもう少し右だ」
そう言って遠くを指差す彼女の手を、上から覆うように掴んで正しい方向に向ける。
手が触れ合っているというのに、彼女はまったく動揺する素振りを見せない。
家族のように親密に接してくれるのはありがたいが、少しは男というものを意識してもらわないと、
シェアハウスは男所帯なのだから取って食われる可能性も……。
考えれば考えるほど心配になるが、景色を楽しんでいる彼女の気分を害することもできない。
私は思考を切り替えようと、車まで戻り、車内から一眼レフのカメラを持ち出した。
「あ。それって前に話してくれたカメラですか?」
「ああ、そうだ。君を撮ろうかと思って持ってきたんだ」
「私を? いえ、あの……私は大丈夫です。それよりも、この綺麗な景色を撮ってください!」
「遠慮することはない」
「あの、でも……恥ずかしいので……」
「そうか? まあ、君が嫌がるなら今はやめておこう」
私はそう言うと、丘から見える街並みと青空をフレームに収めた。
何枚かシャッターを切り終えると、隣りに佇んでいた彼女に視線を向ける。
余程景色が気に入ったのか、それとも別の何かを考えているのか、彼女はとても美しく穏やかに微笑んでいた。
その顔を収めたい欲に駆られ、レンズを彼女に向けてカシャッと一度だけシャッターを切る。
「え……ちょっ、リュウさん! 今、撮りました?」
「一枚だけ」
「撮らないって言ったのに……」
「『今は』と言っただろう」
自分で言っておきながら大人気ない言い訳だと、内心苦笑いを浮かべる。
そんな私を見つめながら、彼女は不服そうな顔をして何かを訴えていた。
「何か言いたそうだな」
「私だけ写るなんて不公平です」
「そんな顔をしなくても……。すまなかった、どうすれば機嫌を直してくれる?
データを消すかい? それとも、帰りに君の好きなものを買おうか」
「いいえ。そのデータは残したままでいいので……リュウさんも写ってください」
突然の提案に一瞬固まってしまう。
私が?
自分のカメラに?
自分を収める?
何が楽しくて?
「それは、できない」
「駄目です。盗撮の罪は重いですからね」
「盗撮だなんて人聞き悪い」
「写真一枚で許しますから。さあさあ、近寄ってください」
「わかったから、そう焦るな」
彼女は楽しそうに目を輝かせ、私に近づいてくる。
またこの距離。危機感がないにも程があるのでは……?
小さくため息をつくと、フレームに収まるよう彼女の肩に手を回して、密着するように引き寄せる。
それと同時に、ビクッと彼女の身体が小さく揺れ、少しだけ動揺の色を見せた。
「どうかしたのか?」
「あ、いえ……なんでもないです」
「耳が赤い気がするが、気のせいかな?」
「いえ、本当になんでもないですから」
彼女の反応にふふっと笑みをこぼして、彼女の耳に唇を寄せた。
「迂闊に近づいた君の責任だからね」
耳元でそう囁くと、さらに距離が縮まるように彼女の肩をぐっと強く引き寄せる。
同時に、その髪に優しくキスを落とし、シャッターを切ったのだった――
END
『ふたりでお留守番』
深夜0時。
紫音の店の手伝いも終わり、コンビニにでも寄って帰ろうかと考えていたら、
ポケットの中で携帯が震えだした。
画面を見ると一通のメールを受信しているのに気づき、ロックを解除して内容を確認する。
メールに視線を走らせると、送信者に目が留まる。
それは思いがけない人物からだった。
「アイツがこんな時間にメールしてくるなんて珍しいな」
送り主はシェアハウスの管理人かつ、俺が想いを寄せている女から。
少し驚きつつも内容を確認すると、
『今日はみんないないので、龍久さんも帰りが遅くなっても大丈夫ですよ』と書かれていた。
なんだ、こいつ。
誰もいないから今日くらい一人を満喫したい的な、そういうことか?
っていうか、紅貴と蒼はわかるとして、優竜もいないって何事だよ。
基本的にはこいつにべったりなのに。
え、待て待て。っていうか、一人危なくね?
『大丈夫ですよ』って何が大丈夫なんだよ。バカかよ。ほんと、バカかよ。
動揺しすぎて二回言っちまったわ。
携帯をポケットの中にしまうと、俺は全速力で走りだした。
向かったのはもちろん、アイツが一人で留守番をしているシェアハウス。
コンビニでアイスでも買って行こうかと思っていたけど、今はそれどころじゃない。
急いで帰り玄関のドアを開けると、その音を聞きつけたのかアイツがリビングから顔を出した。
「あれ? 龍久さん、おかえりなさい。メール見ませんでしたか?」
「見た」
靴を脱いでスタスタと歩きリビングに入ると、上着を脱いでドサッとソファに腰掛ける。
アイツも俺の隣に腰を下ろした。
「龍久さんも遅くなるかと思っていました」
俺の気も知らないであっけらかんとそんなことを言うもんだから、
俺は盛大なため息をついてしまった。
「お前がいるから帰ってきたんだよ、バカ。それくらいわかれっつーの」
「あの、でも……私だって一人でお留守番くらいできますよ?」
「あのなぁ……できるできないの問題じゃねーんだよ」
「じゃあ、どういう問題ですか?」
「ああ言えばこう言う奴だな。最近物騒なんだから油断するなっつってんだよ。
それに、お前が一人でいることを知って放っておけるほど、俺も冷たい人間じゃねーの。
わかったか? バカ」
「そんなに馬鹿って言わなくても」
「バカバカバカバカ。ほんっとバカ」
「ひ、酷い言われよう……」
「何かあってからじゃ遅いんだからな。わかってんのか?」
「はーい」
その間延びした返事が無性に腹立たしくて、両手を伸ばしアイツのわき腹をつかんだ。
そのまま高速でくすぐり始める。
「ちょ! 龍久さん! やめっ!!」
「うるせぇ! 俺様がこーんなに心配してるのに適当な返事をした罰だ」
「あはははっ! ご、ごめんなさい! なんでも、なんでもしますから!」
「本当になんでもするか?」
「します! しますから!」
『しめた』と思い、わき腹からパっと手を離す。
目の前のくすぐられていた本人は、笑い疲れたと言わんばかりの顔をしていた。
「お前、顔やばいことになってるぞ」
「誰がこんな顔にさせたんですか」
「俺だな」
「少しは反省してください」
「さーて。なんでもしてくれるんだよな? 何にすっかなー」
「反省の色なしですか……!」
料理もいいけど、それは今じゃなくても作ってくれるだろうし。
一緒に風呂は……俺が我慢できなくなるからダメだ。色々やばい。
添い寝も……俺の理性クンがすぐにサヨナラするからダメだ。
間をとって――
「膝枕」
「え?」
「よし、決めた。膝枕してくれ」
「え?」
「何度も聞き返すな。ほら、膝貸せ」
ゴロンと横になって、許可が下りていない腿に頭を乗せる。
頭のあたりから柔らかい感触が伝わってくる。
「お前の足、結構寝心地いいな」
「太ってるとでも言いたいんですか?」
「違うって。女っぽい足だなって言ってんの」
「え……」
寝転がったまま下から顔を見上げると、恥ずかしそうに頬を赤く染めているのが視界に入る。
それをひどく可愛いと思ってしまうくらいには、俺はこの女のことを好きらしい。
「まったく。困ったもんだな」
「何がですか?」
「なんでもねーよ。こっちの話」
どんな些細なことでも『可愛い、好きだ』と思えてしまうなんて、恋愛感情とは困ったもんだ。
愛しいという感情を噛みしめながら、くくっと喉を鳴らして笑う。
目の前の女は不思議そうに首を傾げた。
この関係が進展するのは、もう少し先の話――
END
『まるで新婚の朝』
いつもと変わらない朝。
階段を降りてリビングに続くドアを開けると、炊き立てのご飯と醤油の香ばしい香りがした。
紫音が朝ご飯を準備しているのだと思いキッチンに向かうと、
予想外の人物がコンロの前で何かと格闘していた。
「……何やってんの?」
「うわぁ! 紅貴さん、おはようございます」
「うん、おはよ」
「驚かせないでくださいよ」
「普通足音で気付くでしょ。あんた、鈍いんじゃない?
っていうか、何にそんなに熱中してたの?」
「玉子焼きを焼いていたんです」
「玉子焼き?」
彼女に近づいて手元を覗き込むと、フライパンの上にはまだ半熟の卵。
っていうか、なんで玉子焼き? この子が朝ご飯作ってるの?
え、なにそれ。不安なんだけど。
「朝食は紫音が作ってくれたんじゃないの?」
「はい。朝ご飯は紫音さんが準備してくれましたよ」
「え。じゃあ、アンタはなんで玉子焼いてるの?」
「お弁当を作ってるんです」
少し自慢げに言いながら、彼女は固まりかけた玉子を巻いていった。
料理ができるのか不安だったけど、意外と器用らしい。
それにしても、誰の弁当なんだろう……。
「もしかして、蒼に?」
「いえ、違いますよ。蒼さんはもう出かけましたし」
「じゃあ、優竜とか?」
「はずれ。これは自分用のお弁当です」
「自分に弁当作ってるの?」
「はい。お友達とお弁当を持ち寄って交換しようっていう話になったので、
紫音さんに面倒かけるわけにもいかないし、自分で作ってます」
「へー……アンタ、友達いたんだ」
「失礼な。私をなんだと思ってるんですか」
なんとなく、心臓のあたりがモヤモヤし出す。
少しだけ……本当に少しだけではあるけど、俺のためだと言ってくれることを、
心のどこかで期待していたらしい。
「ねえ、それさ。俺にも作ってよ」
「え?」
「いいでしょ? 一人分も二人分もたいして変わらないって」
「でも、紅貴さん今日お休みですよね?」
「そうだけど、アンタが弁当を作ってくれるなら、どこかに出掛けて外で食べる。だからさ、作ってよ」
「いいですけど……私の手作りでいいんですか?」
「うん。むしろアンタの手料理ってレアだから楽しみ」
「じゃあ、紅貴さんの分も詰めますね」
「ん、ありがと」
彼女は自分のより少し大きめの弁当箱を取り出して、余っていた惣菜を詰めて行く。
二つ並んだ弁当箱の中身が同じで、新婚夫婦の朝ってこんな感じなのかな、とか考えてみる。
近くにあった椅子に座って、忙しなく動く彼女を見ていると、尚更そんな気になっていった。
「なんかさ、新婚さんみたいだね」
「え?」
「だから、新婚さんみたいだねって言ってるの」
「二回も言わなくていいですから」
「照れちゃって、可愛いねー。あ、そうだ。新婚っぽく朝のチューでもしてあげよっか?」
「な、何言ってるんですか! 冗談言ってるとお弁当作るのやめますよ?」
「はいはい、ごめんね。もう意地悪しませーん」
ミニトマトを詰めながら、それと同じくらい真っ赤になっている彼女を見て、
自然と笑みがこぼれてしまう。
今日は、いつもと変わらない日になるはずだったけど、
思いのほか、幸せな日になりそうだ。
ま、自分の為に作ってくれた料理を食べられるのは、もう少し先かな。
そんなことを考えながら、いまだに頬を赤くしている彼女の姿を見つめていた。
END
『不器用で心配性』
風呂からあがって短い廊下を歩いていると、
リビングのソファに座りながら、食い入るようにテレビを見ている人物が視界に入った。
よく見ると、髪が濡れているようだ。
「おい」
「蒼さん!びっくりしました……」
「驚かせてすまない。君は、こんな時間まで何をしているんだ」
「見たいドラマがあったので。でも、ちょうど今終わりました」
「そうか」
俺は彼女に近づくと、右手を差し出した。
「?」
「タオル」
「タオル?」
「タオルを貸せと言っている」
「え?」
「いいから」
不思議そうな顔をしながら彼女が俺にバスタオルを渡す。
それを彼女の頭に乗せて、ゆっくりと髪を拭きはじめた。
「え、あ、あの!」
「髪を濡らしたままでは風邪をひくだろう」
「すみません……」
「すまないと思うなら以後気をつけろ」
次の瞬間、少しだけ落ち込んだ様子を見せる彼女を見て後悔をした。
言葉がキツかったかもしれない。
こんな言い方をしたかったわけではないのに……。
俺は手を止めて、適切な言葉を探す。
「その……責めているわけではない。ただ、今の時期は風邪をひきやすいからな。
辛い思いをするのは間違いなく君だ」
「もしかして、心配して……」
「違う」
「でも……」
「断じて違う。菌がこの家に広がることを怖れているだけだ」
「そうですか」
俺の返答とは裏腹に、彼女はとても上機嫌になっていた。
「なんだその顔は」
「なんでもありません」
「なんでもない顔ではないだろう」
「ただ、嬉しいなーと思って」
「喜ぶことなど何も言っていない」
「そうかもですねー」
陽気に鼻歌を歌い出したのが癪で、今度は強めに彼女の髪をわしゃわしゃと拭いてやる。
「うわぁ! 蒼さん痛いですよ」
「うるさい」
「恥ずかしがり屋ですねー」
「はぁ……違うと言っているだろう」
重たいため息をついてから再び手を止めると、彼女を俺を見上げてきた。
「私ばかり拭いてもらってましたけど、蒼さんの髪も濡れてますね」
「風呂に入ったからな」
「今度は私が拭きます」
「必要ない」
「ダメです。風邪をひきます」
「これくらいで風邪をひくわけがないだろう」
「そうやって油断をしていると、本当にひきますよ? ほら、ここに座ってください」
「だから俺は……」
「いーいーかーら」
「はぁ……わかった」
……言い出すとしつこいからな。
心の中でそんな言い訳をしながら、俺はソファに座った。
彼女は俺の首にかかっていたバスタオルを手にすると、そのまま優しく俺の頭を撫でた。
「気持ちいいですか?」
「……ああ。悪くはない」
他人に触られるのは落ち着かないから嫌いだ。
しかし、何故か彼女だけは安心する。
この気持ちはなんなんだ……。
不明瞭な気持ちを抱えたまま、俺は静かに目を閉じた――
END
『髪に触れる』
「ありがとうございました」
最後のお客様を見送ると、カウンターに置いてあったカップとお皿を重ねる。
「ん~……」
別の場所から聞こえた唸り声に小さな笑みをこぼす。
「ゆっくり勉強したいからと言ってここに来たのに、眠ってしまっては元も子もありませんね」
一度手にした食器をカウンターに戻し、彼女が眠っているテーブルへと足を進める。
向かいの椅子に座って頬付をつくと、彼女は再び小さな唸り声を上げた。
どんな夢を見ているのでしょうか。
何かに追われる夢か、もしくは好きな食べ物を龍久に奪われてしまった夢か……。
「ふふっ。眉間に皺が寄っていますね……」
ゆっくりと手を伸ばし、そこに触れるとぴくっと眉が動く。
ああ、起こしてしまったかもしれない。
そう思ったけれど、彼女の寝息は続いていた。
「なかなか起きそうにないですね」
最近レポートやテスト勉強で眠る時間がなかったようですし、たまには休憩も必要ですよね。
そういえば、優竜から勉強を教えてもらいながらぼーっとしていた時もありましたね……。
「頑張るのもいいですが、ほどほどにしないと倒れてしまいますよ」
彼女の髪に触れて優しく撫でると、眉間の皺が消え、気持ちよさそうな笑みを見せた。
そのまま髪を一束手に取ると、弄ぶように指で触る。
妹のように思いたいのに、最近はそれが難しくなってきている気がする。
この想いを、これ以上膨らませる訳にはいかないのに、
貴女が近くにいて、貴女と話して、貴女に触れると、
思うように気持ちを整理することができないんです。
私が、しっかりしなければいけないのに……。
「はぁ……駄目な大人ですね……」
彼女の髪から手を離すと、音をたてないように立ち上がり、少しだけ歩を進めて彼女の隣に立つ。
そのまま身を屈めて、彼女の髪に口づけをした。
髪へのキスは『思慕』の証――
「私の、本当の気持ちです……」
伝えられない想いを胸にしまい込み、小さなため息をつくと、
彼女の口から吐息が漏れ、ゆっくりと瞼が開いた。
「ん……」
「おはようございます」
「あ……私、寝てしまったんですね……」
「ええ、それはもうぐっすりと」
「すみませんでした。居心地がよくて、つい……」
「そう言っていただけて嬉しいです。もうお店は閉めましたので、一緒に帰りましょうか」
「はい!」
「帰りに何か食べて行きますか?」
「えっと……もしよければ、紫音さんが作ったものが食べたいです」
「え……」
「私、紫音さんが作ってくれるご飯がお店の料理よりも好きなんです!
あ、でも……こんな時間から面倒ですよね。すみません……」
予想外の言葉に驚きながらも、嬉しい気持ちが込み上げる。
緩む口元を隠すように、口元に手を添えた。
「わかりました。では、帰る準備をしてきますね。
待っている間、何が食べたいか考えていてください」
「はい!」
カウンターに置いたままの食器を手にすると、キッチンの中に入る。
流し台に食器を置くと、そのままズルズルとしゃがみこんだ。
「本当に、困りましたね……」
――また一つ、愛おしい気持ちが増えた気がした。
END
『幸せな時間』
大学の眠たい講義も終わり、ざわついている講義室の中に彼女の姿を探す。
あれ? いないみたい。
今日の講義は終わったはずなんだけど、どこ行っちゃったのかな……。
心の中でため息をつき、まだ学内にいるであろう彼女を探しに行く。
ほんの少しの時間しか離れていないのに、早く会いたいと気持ちが逸るのは、
彼女が僕の中でそれほど大きな存在だからだと思う。
「あ……いた」
誰もいない空き教室の扉を開くと、机に向かって難しい顔をしている彼女の姿を見つけた。
集中しているのか、僕が探しに来たことにまだ気づいていないらしい。
「こんなところにいたの? 探したよ」
「あ、優竜。ごめんね、連絡すれば良かったね」
そう言った彼女の目の前には、課題らしきものが広がっていた。
「これって、さっきの講義で出された課題?」
「うん、そうだよ。苦手な内容だから、早めに終わらせようと思って」
「ふーん、それで難しい顔してたんだ。僕で良かったら手伝うよ」
「え、でも帰るの遅くなっちゃうし……悪いよ」
「遠慮なんかしなくていいのに。
二人でやった方が早く終わるし、それに……僕が君と一緒に居たいだけだから」
「ふふっ、ありがとう。じゃあお願いしてもいいかな」
「うん、まかせて」
彼女は再び課題と向き合い、講義室内にはペンを走らせる音だけが響く。
僕は後ろから覗き込むように、その様子を見つめた。
手伝うって言ったけど、自力で問題を解いてるし。
僕、意外とやることないかも……。
邪魔しちゃいけないっていうのはわかってるんだけど、僕がいるって忘れてないよね……?
そんなことを考えていると、さっきまでスラスラと動いていた彼女の手が止まった。
「ねえ、優竜。この問題がわからないんだけど……」
「どこ? ああ、これは……」
座っている彼女を後ろから覆うようにして、問題の解説をする。
本当はこんなに密着しなくていいっていうのはわかってるんだけど、
少しでも彼女の意識に入り込みたくて、必要以上に近づいてみた。
だけど、彼女は僕の期待とは裏腹に、『ああ! 分かった!』と納得したような声をあげると、
また課題の方に集中してしまった。
なんの反応も無いなんて……彼女は僕のことを男として意識していなさすぎじゃない?
そんなことを考えて、自分の気持ちが沈んでいくのが嫌でもわかった。
こうなったら……と、後ろから顔を覗き込み、至近距離で彼女の目を見つめる。
「ねえ、こんなに近くにいるのに……ドキドキしたりしないの?」
「え?」
彼女がはじかれたように僕の顔を見る。
「やっとこっち向いた」
「もう……。課題、早く終わらせなきゃ帰れなくなっちゃうよ」
「君と二人きりでいられるなら、帰れなくなるのも悪くないかなって」
「またそんなこと言って……」
「僕は本気だよ。君がいるならどこへでも行くし、一緒にいたいって思う」
「はいはい、ありがとう」
「また、そうやって……」
僕の言葉を軽く流す彼女を尻目に隣の席に座わったものの、
特にやることもなく、隣にいる彼女の横顔をじっと見つめる。
視線を感じたのか、彼女はふと顔を上げこちらを見た。
「ねえ、優竜? 静かにしてくれるのは嬉しいんだけど、
その……見られてると落ち着かないというか……」
「だって、暇だから」
「暇って……私の顔見てても面白くないでしょ?」
「そんなことないよ」
彼女の両頬に手を添える。
「普段の笑ってる顔も、嬉しそうな顔も大好きだけど、真剣な顔も良いな……って」
「またそうやって……」
「照れてる?」
「照れてませんー!」
そう言うとプイッと反対側を向いてしまう。
少しやりすぎたかな、と心配になったのも束の間、再び彼女がこっちを見た。
「私も、優竜の笑う顔……好きだよ」
「え……」
頬を染めながら言う彼女に、少しだけ顔に熱が集まっていくのがわかった。
「優竜、顔真っ赤だよ」
「不意打ち……ずるい」
「ふふっ、お返し」
頬を染めながら悪戯っぽく笑う彼女に、熱くなった頬が緩む。
あぁ、幸せだな……
そんな気持ちが胸いっぱいに広がっていく。
「このままずっと一緒にいたいな」
そう小さく呟いた言葉が彼女に届いたかはわからないけど、幸せそうに笑う彼女を見て、
『この幸せな時がいつまでも続きますように――』
そう心の中で願った。
END
※これは過去(龍国)のifストーリーです
※主人公は『龍国の皇女』という設定です
『龍国と桜』
これは、龍国が美しい国だった頃のお話――
「姫様、お待ちください」
宮廷の長い廊下を早足で通り過ぎて行くのは、
皇族の第一皇女と、宮廷に仕える王族、紫龍族の日辰紫音だった。
「待ちません」
「これから思想史の講義なんですよ?」
「こんなに晴れて陽気な日に、部屋にこもって勉強なんてやってられないよ」
「そう仰らずに」
彼女は尚も早足で駆けていき、急に角度を変えて角を曲がろうとした。
……が、何かにぶつかってしまい、その勢いで後ろに倒れそうになる。
寸前のところで誰かに肩を抱きかかえられ、尻もちをつくのは阻止できた。
彼女がゆっくりと顔を上げると、そこにいたのは――
「うわ、リュウ……」
「これはこれは、姫君ではないですか」
本性の見えない笑みで彼女を見下ろしているのは、
紫音と同じ王族で白龍族の白霧リュウだった。
まずい人に見つかったと、来た道を戻ろうとした彼女の肩を、
リュウはしっかりと抱き締める。
「姫君。そんなに慌ててどこへ行くおつもりですか?
そろそろ次の講師が見えるはずですが」
「いや、その……ちょっと散歩に」
「ああ、リュウ。いいところに。助かりました」
「いや、いいんだ。ここに来るのは予測できたからね。
紫音、お転婆な姫を君一人に任せてすまない」
「お転婆な姫って私のこと?」
「他に誰がいると思う?」
「失礼……」
「さしずめ、勉強が嫌で紫音を困らせているんだろう?」
「違っ……わないけど……」
はぁ、と小さなため息をついたリュウは彼女から手を離し、軽くその額を小突いた。
「まったく、一国の皇女とは思えない行いだ」
「リュウ、姫様に向かって失礼ですよ」
「わ、私だって、たまには息抜きしないと死んじゃうよ……」
「『死ぬ』だなんて、軽々しく言葉にすべきじゃない」
「……ごめんなさい」
このままいくと重い空気になりかねないと察した紫音は、少し考えを巡らせてから、
優しい顔で口を開いた。
「今日くらいは、いいことにしませんか?」
「どういう意味かな?」
「彼女、最近毎日頑張っていますし、徐々に覚える速度も上がってきているんです。
なので、今日くらい息抜きをする時間があってもいいと思いませんか?」
「……だが……」
「講師の方には、私から話しておきますし、きちんと帝にも許可を頂きますから」
紫音の提案にキラキラと目を輝かせる皇女。
彼女の集中力が切れている以上、強要するのは効率が悪いと判断したリュウは、
自身の額に手を当てながら小さなため息をついた。
「……はぁ、わかった。では、今日だけ二人でゆっくり過ごすといい」
「え、ダメダメ。みんなも参加するんだよ」
「私には仕事がある。君の面倒をみている暇はない」
「『リュウは今日非番なのに働いている。どうにか休ませたい』
ってお兄様が嘆いていたけど?」
「皇子が……。余計なことを……」
「ってことで、みんな誘ってお花見しようよ」
「たまにはいいじゃありませんか」
「……わかった。君たちは二人とも、一度言い出すときかないからな」
「ふふっ。それじゃあ、私がみんなに声をかけるよ。
集まるのは、いつもの場所でいいかな?」
「ああ、頼んだよ」
数刻して、皇女がいつもの場所に足を運ぶと、すでに『みんな』が集まっていた。
黒い服を纏った黒龍族の一人、黒生龍久。
青い服を着ているのが青龍族の一人、御龍蒼。
赤い服で桟橋に寄りかかっているのは赤龍族の一人、飛龍紅貴。
そして、彼女の存在に一番最初に気付いたのは、
黄色い服を着た黄龍族の一人、黄門優竜だった。
「……あ、やっと来た。待ってたよ」
「おっせーんだよ。早く来い」
「やーっと来た。アンタ待ちだよー」
「ごめんなさい、ちょっと着替えに時間がかかっちゃって」
「ほら見て、桜……。満開だよ」
「本当だ。とっても綺麗だね」
「この桜、君に似合いそう」
そう言って、優竜は彼女の髪に桜の花を飾る。そして、満足そうに優しく微笑んだ。
「やっぱり、僕の思った通り。すごく可愛いよ」
「本当? ありがとう」
「馬子にも衣装だな」
「彼女も、お前には言われたくないだろうな」
「ああ? またお前か、リュウ。うるせっつーんだよ」
「おーい、ユウくーん。そこでいちゃついてないで早くお花見始めようよ」
「俺も暇ではない。この後も稽古がある。早く始めて早く終わらせるぞ」
「ふふっ、蒼。今日はゆっくりするのが目的なんですから、
そんなにせっかちにならなくても」
「……わかっている」
みんなで紫音が用意してくれた豪華なお弁当を囲むと、全員に飲み物が渡された。
「あれ? 酒ねぇのかよ? 酒」
「おい、万年酔っ払い。少しは禁酒という言葉を覚えろ」
「うるっせーな。今日は仕事ねぇんだからいいだろうが」
「そういう問題じゃない。昼間から宮廷で酒を飲むなど言語道断だ」
「あー、ヤダヤダ。これだからお堅い官僚殿は」
「なに?」
「ちょっとちょっとー。せっかくの花見なんだし、今日くらい仲良くしなよ」
「コウくんの言うとおりだよ。こんなに綺麗な桜の下で喧嘩なんてよくないと思う」
「わかっている。龍久のことは放っておいて、食事を始めようか」
全員で桜の木の下で食事を始めると、優竜がポツリと言葉を発した。
「桜の花びらを最初に掴んだ人は願いが叶うっていう遊び、知ってる?」
「へぇ、そんなのがあるんだ! 優竜、物知りだね」
彼女が感心するように微笑みかけると、優竜も少しだけ表情を和らげた。
「この前、女官達が話しているのを聞いただけなんだけどね。
そういうまじないみたいなのがあるらしいんだ」
「なんだか、楽しそうだね!」
「それでね……やって、みない?」
優竜から何かを提案するのは初めてだったため、
全員が驚いたような表情で優竜を見つめた。
その様子に焦った優竜は、すぐに気まずくなって俯いてしまう。
「あの、別に……絶対とかではなくて……。
その、彼女も楽しそうだって言ってくれたし……」
「いいんじゃね? 優竜がやりたいって言うなら、俺は付き合ってやるよ」
「そうだな。たまには俺もそういったことに参加してもいいと思っていたところだ」
「思っていたところだって、蒼は素直じゃないねー」
「紅貴、うるさいぞ」
「はいはい。俺もやるよ」
「私も参加させて頂きますね」
みんなが楽しそうに立ち上がるなか、リュウが優竜の頭を優しく撫でた。
「たまには、自分の意思を言葉にするのも悪くはないだろう?」
「うん……」
「優竜がこうやって提案してくれて、私も嬉しいな」
「君にそう言ってもらえると、僕も嬉しい」
「姫君は、もう少し自分の言動に気を付けてほしいものだが」
「ほら、リュウの小言が始まる前にみんなのところに行こう」
彼女は優竜の手を掴んで桜の木の麓へと駆け出し、優竜も彼女の後に着いていく。
「まったく、手のかかる姫君だ」
口調は淡々としているものの、リュウの口元は柔らかく微笑んでいた。
全員が桜の麓に集まると、紫音が簡単な流れを説明する。
各々納得したように返事をするなか、彼女だけが異論を唱えた。
「ちょっと待った! 身長差がありすぎて、勝てる気がしないです」
「まあ、それはアンタが頑張るってことで」
「紅貴ひどい……。あの、提案なんだけど! 二人一組にしない?」
「あ? ねーわー」
「龍久の意見は無視します」
「姫さん、どんどんリュウに似てきたな……」
「ってわけで、私は蒼と組むので、各々好きな人と組んでください」
「どうして俺が……」
「身長が一番高いから、有利かなって」
「アオイ君、ずるい……」
「っていうか、それだと一人あまるよ? 残ったの奇数だし」
「ふふっ。じゃあ、私はここで審判をしますね」
紫音はそう言って、近くの岩場に腰掛けた。
残った四人が顔を見合わせると、一瞬の沈黙が流れる。
「あー……ユウくん、一緒にやろうか」
「は!? ちょっと待て! 紅貴! お前は俺様と組め!」
「やだよ。龍久、がさつで花びら掴めなさそうだし」
「では、私と組もう」
「リュウ君もやだ。取れなかった時、俺のせいにされたくないし」
「僕は、別にいいけど……」
「はい、決定ー。俺とユウくん。リュウ君と龍久。蒼と姫ね」
「無理だって!」
「それじゃあ、始めますよ?」
「ちょっと待て。私の異論も聞くべき……」
「手のひらは禁止。人差し指と親指で掴んでくださいね。それでは、開始!」
リュウと龍久の話を無視して、紫音は開始の声をあげた。
紅貴と優竜が花びらを掴もうとするものの、今日は適度に風が吹いており、
なかなかうまく掴むことができず、
リュウと龍久に至っては口喧嘩をしながら掴もうとするため、
花びらが余計に舞ってしまう始末だった。
一方、蒼と彼女は――
「うっ! はっ!」
飛び跳ねながら、高いところに舞う花びらを掴もうとする彼女。
その姿に見かねた蒼は、静かに彼女の後ろに立った。
「そんなに跳ねていては、身体が安定しないだろう。
下の方で花びらを取ればいいものを」
「あ、たしかに」
「……まあ、今回は手伝ってやろう」
そう言った瞬間、蒼は彼女の腰を抱きしめてそのまま上に持ち上げ、
彼女を自分の肩に座らせた。
「うわぁ……!」
「どうだ? 取れそうか?」
「あ、うん!」
桜の木からちょうど離れ落ちた花びらを、彼女が上手に掴む。
「蒼! 取れた! 取れたよ!」
「そうか、よかったな」
喜ぶ彼女の顔を見て、蒼の口元も少しだけ綻ぶ。
彼はそんな自分に気付いて、またすぐにいつもの無骨な表情に戻した。
「おや、どうやら姫様が一番のようですね」
「ふふっ、蒼のおかげだよ」
「つーか! 蒼! テメェなんで姫さん担ぎ上げてんだよ!」
「作戦のうちだ」
「姫君を担ぎ上げるなど危険だろう。早く降ろすんだ」
「二人とも嫉妬してるー」
「「違う!」」
紅貴の言葉にリュウと龍久が声をそろえて反論すると、紅貴は声を出して笑い出した。
「二人とも仲良しだなー」
「紅貴、それ以上私をからかうと酷い目にあうが、いいんだな?」
「はいはい、すみませんでしたー」
蒼の肩から降りた彼女の元に、紫音がゆっくりと近づき、優しく頭を撫でる。
「よかったですね」
「蒼のおかげだよ」
「俺は何もしていない。持ち上げただけだ」
「ねえ、君の願い事ってなに? 僕、知りたい……」
「そっか、願い事……蒼は?」
「俺の権利は君に譲る。俺の願いは自分で叶えるから問題ない」
「ふふっ、さすが蒼だね。んー、じゃあそうだな……」
彼女は、大きな桜の木を見つめながら、じっくりと考え、静かに呟いた。
「ずっとこのまま、みんなで一緒にいたい……」
「え?」
「毎年、春になったらここでお花見をして、夏になったら西瓜を食べて、
秋は紅葉を楽しんで、冬になったら雪で遊んで、また春がきたらお花見をして……。
この先もずっと、みんなで一緒に幸せな日々を送りたい。
って……ちょっと個人的すぎたかな?」
彼女が遠慮がちに笑うと、リュウがそれを否定するように首を横に振り、
その場に片膝をつく。そして、優しい眼差しで彼女を見上げた。
「私達が、この暮らしが続くように、この龍国を、この宮廷を、
そして……姫君をお守り致します」
その言葉に続くように、全員が片膝をついた。
「大切な姫様の為、尽力しますね」
「僕も……」
「まっ、お前は俺が守ってやんねぇとピーピー泣きそうだしな!」
「アンタのためなら、俺もやれることはやるよ」
「……そのために日々鍛えている」
「姫君の願い、私達が必ず叶えます。皇族に仕える、王族の誇りにかけて」
そう言って、全員が頭を垂れる。
彼女は幸せに満ちた表情で、ゆっくりと頷いた。
「よろしくお願いします」
これは、龍国が侵略される前のお話――
END